054-248-3999
【診療時間】9:00〜12:00/15:20~17:30
【休診日】日・祝・第4水曜日、水・土午後

おしり・おなか
肛門外科
大腸・肛門疾患について
肛門疾患は、①痔核(イボ痔)②裂肛(切れ痔)③痔瘻(あな痔)と肛門周囲膿瘍④直腸脱と、大きく分け区別し名を呼んでいます。痔核には「内痔核」と「外痔核」があります。

①痔核(イボ痔)
保存治療
■内痔核――痛みは伴わず出血や腫れ、脱出があり、初期の頃では異物感などが感じられます。脱出の程度によりⅠ度~Ⅳ度に分類されます。

I度:痔核の塊は肛門の外に脱出することはないが、排便時に出血することがある。
II度:排便時に痔核が脱出しても、中に自然と戻る。
III度:排便時に痔核が脱出すると戻らず、指で押し込まないといけない。
IV度:痔核が肛門外に脱出したままのもの。脱肛と呼ばれる。
≪治療方法≫ 軟膏や座薬で治療し、軽度の症状には外来にて硬化療法やゴム輪結紮法を行ないます。処置は4~5分で終わります。出血や痛みがある場合には手術治療を行います。
≪手術治療≫ 当クリニックでは痔核のあるところだけを切除する結紮切除術を行いますが、2種類の麻酔(脊椎麻酔と硬膜外麻酔)を行ない、止血コントロールをする工夫もしておりますのでご安心ください。軽度の場合は日帰り手術も可能です。
■外痔核――突然痛みを伴ったやや青紫色の血栓のしこりが肛門の縁にできます(血栓性外痔核)。便秘、下痢、アルコール、長時間座ったままなどの原因があります。

≪治療方法≫ 軟膏や座薬で治療します。強い痛みや腫れが引かない場合は局所麻酔をし血栓除去手術を行います。内痔核の腫れが伴う症例もありますので適切な判断をお任せください。
■嵌頓(カントン)痔核――内痔核が大きく腫大脱出し、循環障害により痔核表面が腐りかけ、周囲にかなり強いむくみと痛みを伴います。

≪治療方法≫ 軟膏と腫れ止めの内服薬で数日経過を観察し腫れを冷やします。多くの症例ではこれで快方にすすみます。普段から繰り返し症状がある方には手術をお勧めします。
ジオン注(ALTA療法)~痔の新しい治療法
ジオン注(ALTA療法)とは、排便時に飛び出す内痔核に対して、痔を切らずに注射で治療をする画期的な方法です。一つの痔に対し、4ヵ所ほどジオンを注入し、内痔核に無菌性の炎症を起こさせ消失させます。手術時間も7 ~ 10分程度で完了し、注射した翌日には出血や脱肛が治まります。日帰りで手術できますが翌日も休まれることをお勧めしています。

(1)痔核上側の粘膜下層(2)痔核中央の粘膜下層(3)痔核中央の粘膜固有層(4)痔核下側の粘膜下層
手順について
①硬膜外麻酔で痛みを抑えた後、静脈麻酔で眠って頂きます。
②ジオンを注入します。殆どの方は知らないうちに終わってしまいます。
③処置後は2~3時間で目�が覚め、帰宅できます。
④4~7日後、再受診にお越しください。
⑤その後は2~3週間おきに約2ヶ月通院し、完治となります。
≪ジオンを投与するとどのようになりますか?≫


投与後早い段階で痔核への血液量が減り、翌日には出血が止まります。脱出も治まってきます。
次第に痔核が小さくなり、伸びていた支持組織も元の位置に戻って脱出がみられなくなります。(1週間〜1ヶ月)
その後、出��血がみられなくなり、脱出や肛門のまわりの腫れもなくなります。
≪ジオン治療に関して≫
ジオンのオペ料金は3割負担で18000 ~ 20000円くらいです。また、現在は入院を取りやめ、病棟は無い状態です。
検査やオペ後は個室として使用しています。宜しくご対応願います。
期間・・・手術は日帰り、三週間後までは、週に1回ほど通院して頂き、問題が無ければ終診となります。
リスク・・・手術後は個室にて休んで頂きます。2~3時間ほどで安静は解除されます。
≪投与後の生活≫
・当日の入浴はできませんがシャワーを浴びることはできます。入浴は翌日からです。
・ノンアルコール飲料を含め、アルコール類は完治するまで飲むことができません。辛い香辛料、カレー、コーヒーなどの刺激物は3週間ほどお控えください。脂っこい食事はしばらくお控えください。
・お仕事の復帰は翌日から可能ですが、2週間ほどは重い荷物を持つなどお尻に力が入ることはおやめください。
・自転車、自動車、オートバイの運転は1週間ほど避け、長く座り続ける場合は深く腰掛け、1時間毎に立つ・歩くなど休憩をはさむようにしてください。
②裂肛(切れ痔)
■急性裂肛――肛門の上皮が浅く裂けている状態です。トイレットペーパーにつく程度の軽い出血がみられます。発症から日は浅く、排便時に痛みがあります。

≪治療方法≫ 軟膏や座薬で治療します。何ヶ所も切れていたり肛門の緊張がある場合には、局所麻酔をし肛門括約筋を伸ばしたり切開する方法もあります。
■慢性裂肛――いつも同じ場所が切れ、その周辺にポリープなどができた状態です。裂け目が深くなり(肛門潰瘍)、周囲に炎症が起きて肛門が細くなります(肛門狭窄)。また化膿してしまうこともあります(化膿性肛門潰瘍)。

≪治療方法≫ お薬では改善しないため、肛門を広げる手術を行います。患部を切開または切除し肛門を広げます。皮膚を補うため外側の皮膚を一部ずらして、直腸粘膜に縫い付ける方法をとることもあります。1泊2日の入院手術になります。
③肛門周囲膿瘍と痔瘻(あな痔)
細菌が入り込み肛門周辺に強い炎症が起きて膿んだ状態を肛門周囲膿瘍、炎症が少し落ち��着いて肛門の中と外がトンネルでつながっている状態が痔瘻(あな痔)です。痛みや、時には発熱や排便障害なども伴います。痔瘻は、しこりのみの場合や押せば痛みを感じたり、常に分泌物が出ているなどの状態があります。
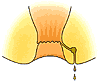
≪肛門周囲膿瘍の治療≫ 局所麻酔、あるいは腰椎麻酔(下半身麻酔)をし、膿を取り除く手術をします。術後は炎症が治まれば治癒する方もいますが、半数以上は痔瘻が形成されます。
≪痔瘻の治療≫ 手術にて根治療法を行います。切除する方法、瘻管を開く方法、くりぬく方法などがあり、痔瘻の場所や形・広がり方で方法を選択します。この他にはゴム等で縛り徐々に切っていく方法(シートン法)もあり、クローン病における痔瘻の治療に用いられている方法です。
④直腸脱
直腸が、支持する組織の緩みによって垂れ下がり肛門より脱出します。同時に肛門括約筋にも緩みがあります。
≪治療方法≫ 脱出した部分を中に戻すには手術が必要です。数十か所粘膜を糸で縛ると直腸は縫縮され中に戻ります。同時に肛門括約筋の緩みも締めます。この他には開腹手術で直腸を中に戻す方法もあります。
消化器内科
胃カメラについて
■胃カメラのすすめ
当クリニックでは、テレビの大画面で画像を観察しながら検査ができる電子内視鏡を採用しています。内視鏡の機械もわずか直径8mmと細くて�柔らかいものを使用しており、検査前には麻酔も行うため楽に検査を受けていただくことができます。
胃の中を直接観察するので早期胃癌の診断には非常に役立ちます。また、誤飲の摘出や吐血した際の止血など様々な治療も内視鏡ですることができます。

ピロリ菌の検査と除菌
ピロリ菌に感染すると急性胃炎が発生し胃潰瘍や十二指腸潰瘍が慢性化します。そこからポリープや癌ができやすいことが分かっているため、必要な検査をしてピロリ菌をしっかり除菌しましょう。
≪除菌は1週間で一気に≫ お薬の服用を1日2回、1週間続けます。抗生物質による下痢などの副作用がみられることがありますが、ほとんどは軽症です。
≪保険適用≫ 胃潰瘍または十二指腸潰瘍と診断された患者様には保険が適用されます。ピロリ菌に感染したすべての方が対象ということではありませんが、除菌することにより、癌の予防にも繋がるためしっかりと除菌しまし��ょう。
≪除菌後≫ 1~12ケ月後にその後の判定をするため内視鏡検査をします。除菌後も維持療法を必要とする場合があります。
大腸内視鏡検査について
■大腸内視鏡検査のすすめ
大腸癌患者数は40歳代から増加し、最も多いのは60歳代です。家族に大腸癌になった人がいる、大腸にポリープがある、大腸癌とは別の癌の既往症がある、潰瘍性大腸炎・クローン病などの炎症性腸疾患があるなどといった方は注意が必要です。
自覚症状の無いうちに大腸癌を発見するため便潜血検査がありますが、検査結果が陽性だった方には大腸内視鏡検査を行い、大腸癌の早期発見・早期治療をし、治癒を目指します。

≪大腸内視鏡でできること≫ ポリープ型の早期癌は内視鏡下で切除ができます。陥凹型や平坦型の早期癌はその粘膜下に生理食塩水を注入し、浮き上がらせた後、電流を使って摘出します。いずれも完全に切除されていれば、開腹手術の必要はありません。
検査の流れ
①外来を受診してください。
――特別な準備は不要です。検便や診察を行います。
②検査が必要な場合
――大腸内視鏡検査が必要となった場合は、検査の日程をご予約ください。
③検査の2~3日前、前日
――2~3日前からゴマ、種の多いもの(キウイやキュウリ)、こんにゃく、きのこ、海藻類の食事をやめ、前日には夜寝る前に下剤を飲みます。
④検査当日
――朝8:30ごろから、ゆっくり2時間以上かけて2リットルの水の下剤を飲みます。ウォシュレットトイレ付きの個室もご用意しております。
⑤麻酔
――ご希望の方には麻酔をすることができます。生体監視モニターで麻酔中の管理をしますのでご安心ください。
⑥検査
――お昼過ぎごろから検査を始めます。じっくりと観察し、早期癌を発見した場合には切除を行います。検査は1時間ほどで終わります。
⑦検査後
――休憩していただけましたら、検査結果のご説明をいたします。
⑧10~14日後
――外来にお越しいただき、顕微鏡で調べた結果をご説明いたします。
外科
ヘルニアについて
臓器の一部が、元々あるべき場所からずれている状態のことをヘルニアといい、すぐに思い浮かぶような椎間板ヘルニアの他にも、実は様々な種類のヘルニアがあります。

鼠径ヘルニア
下腹部のやや外側で脚の付け根の鼠経(そけい)を通ってお腹の中の臓器が付きだしてしまう病気です。幼児期と50~60才代男性に多くみられます。鼠径部の膨らみが次第に戻らなくなり、完全に突き出してしまい強い痛みをともなう状態を嵌頓(カントン)と呼びます。嚢の出口が締め付けられると腸閉塞を起こしてしまいます。

≪治療方法≫ 当クリニックでは局所麻酔で手術を行います。ご希望があれば眠っている間の手術もできます。2~3日泊の入院か状態によっては日帰り手術も可能です。退院後ほとんどの方はは1~2回の通院で終了します。
大腿ヘルニア
鼠径部のやや下方、大腿部の部分�にヘルニアが起こる病気です。女性に多くみられます。自覚症状が少なく嵌頓しやすいため、腸管の壊死を起こしやすく、注意が必要です。
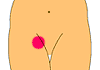
≪治療方法≫ 鼠経ヘルニアと同様��に局所麻酔で飛び出し口を塞ぐ手術を行います。